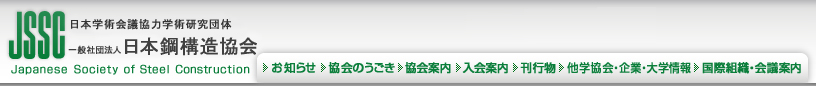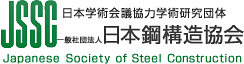
協会案内
会長ごあいさつ
一般社団法人日本鋼構造協会会長 緑川 光正

明けましておめでとうございます。日本鋼構造協会は昨年、設立60 周年を迎えることができました。これもひとえに、会員の皆様をはじめ関係官庁・関係団体の温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。
さて、私達がこの3 年間取り組んできた第10 次中期3ヵ年計画では、カーボンニュートラルを戦略課題として掲げ、「鋼構造カーボンニュートラル特別委員会」を新設しました。その中で、環境面での優位性を鋼構造の新たな魅力として位置付け、脱炭素・循環型社会の実現を目指した取り組みを行いました。他方、「鋼構造未来戦略小委員会」では、若手技術者が中心となって、GXやDXを推進力とする鋼構造の新たな技術戦略を議論してまいりました。
昨秋の鋼構造シンポジウム2025では、60 周年記念・特別セッション「鋼構造の未来について考える」を開催し、両委員会の活動成果や新中期に向けた提言について報告しました。これらの検討結果を踏まえ、前中期の継続課題を整理した上で、本年より第11次中期3カ年計画へ移行し、さらなる飛躍を目指してまいります。
新中期計画では、第一の柱として「鋼構造生産システムの革新」を掲げます。少子化や労働人口の減少に対応するため、建設分野においてもDX が注目されていますが、その要諦はデジタル技術の単なる導入ではなく、従来の枠組みや働き方を抜本的に改革することにあります。一方で、サーキュラーエコノミーの観点からは、構造物の資源循環が新たな課題として浮上しています。環境負荷を低減するため、破壊的解体に依存するのではなく、設計段階から素材・部材への分離性に配慮した構工法の実現が求められています。こうした社会的要請を踏まえ、鋼構造の強みと特徴を最大限に活かしつつ、未来の生産システムのあるべき姿を提案して参ります。
第二の柱は、「カーボンニュートラルに対する技術戦略の具現化」で鋼構造カーボンニュートラル特別委員会の活動を継続します。前中期で纏めた「鋼構造の特性を踏まえた環境負荷評価法」については、内容を分かりやすく整理するとともに、鋼材・鋼構造の環境負荷が適正に評価されるよう、関連団体への働きかけや対話を推進します。また、設計・製作・施工等を対象とした「環境負荷低減に資する鋼構造技術」については、これまでの基礎検討を踏まえ、具体的な技術戦略を策定し、実行に移します。
前中期では建築分野を中心に取り組んできましたが、新中期では土木分野およびステンレス分野にも検討対象を拡大する計画です。
第三の柱は、「国際展開に関わる取り組みの加速」です。当協会では、「国土強靭化」および「生産性向上」を主要技術課題として位置付け、社会ニーズに応える取り組みを進めており、各種成果が続々と公表されつつあります。これらの成果の英文化ならびに国際標準化を積極的に推進し、我が国の優れた鋼構造技術を国際社会へ発信します。
現在、JSS 規格「建築鉄骨溶接部の機械的性質の標準試験マニュアル」を基礎とした国際標準案をISO に提出し、審議を受けています。日本発・世界初となる本件の成案化を着実に進めるとともに、次なるテーマの検討を開始し、国際展開を加速させてまいります。
第四の柱は、「若手技術者の育成」です。人材育成・技術伝承の観点から、2023 年に協会ホームページに開設したデジタルアーカイブの強化を継続しております。現在、学生向けに鋼構造の魅力を発信するPR 活動を進めており、新中期では若い世代の関心を引く動画コンテンツの公開を計画しています。
一方、鋼構造研究助成事業では、過去21年間で118 件を採択し、若手研究者の育成に貢献しています。2009 年に始まった鋼構造技術者育成講習会は、累計3 万5,000 名以上が参加し好評を博しています。さらに、実務的な技術者資格として高く評価されている土木鋼構造診断士や建築鉄骨品質管理機構を運営し、鋼構造の安全・安心および品質確保に寄与しています。
日本鋼構造協会は、輝かしい未来の実現に向け新たな一歩を踏み出します。新中期では、成長戦略をしっかりと描きながら社会課題の克服に取り組む所存です。会員の皆様ならびに関係各界の皆様におかれましては、引き続き本協会の活動に対し、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
(以上、2026年 年頭の挨拶より)
Copyright (C) 2008 Japanese Society of Steel Construction. All Rights Reserved.